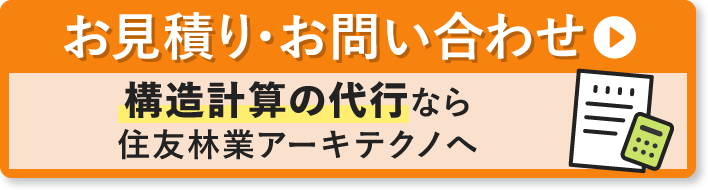構造計算とは?種類や計算方法、かかる費用について解説

目次
構造計算とは?
構造計算とは、建築物を建てるにあたって、建物の構造の安全性や、地震や風雨に対する耐久性を確かめる計算方法です。建物の構造や性能が、荷重・地震・風圧などのさまざまな負荷に耐え得る設計になっているかを、規定の方法に従って算出します。構造計算がなければ構造設計もできないため、建築においては重要な業務の1つです。
2025(令和7)年4月には、建築基準法の「審査省略制度」(通称「4号特例」)が改正 されました。この法改正によって構造計算がどう変わったのか、詳しく見ていきましょう。
構造計算に対する「4号特例」縮小の影響
構造計算が必要とされる建物は、建築基準法によって定められています。これまでは、木造2階建て以下、延床面積500㎡以下、高さ13m以下あるいは軒高9m以下という条件を満たす木造住宅、また非木造で延床面積200㎡以下の平屋は「審査省略制度」(通称「4号特例」)によって、建築確認申請時の構造審査を省略することが認められていました。
しかし、2025年4月からこの特例が縮小化され、構造審査を省略できるのは、構造にかかわらず平屋かつ延床面積200㎡以下の建物のみとなりました(※)。これによって、現在は構造計算を必要とする建物が増え、建築にかかわるハウスメーカー・工務店・設計事務所などは構造計算業務の負担増に直面していることでしょう。
ここからは、4号特例の縮小によって影響を受けている建築関係者に向けて、構造計算の概要や計算方法、外注費用などについて詳しく解説します。
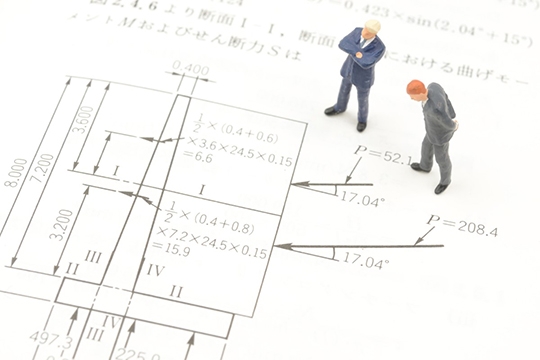
建物にかかる荷重は2種類ある
構造計算で重要なのは、建物にかかる力の流れです。柱ごとに伝わる力や、梁・壁が負担する力などを緻密に算出し、建設コストにも配慮しながら構造を検討しなければなりません。
この建物にかかる力を荷重といい、主に鉛直荷重(えんちょくかじゅう)と水平荷重(すいへいかじゅう)の2種類があります。それぞれについて、具体的に見ていきましょう。
鉛直荷重
鉛直荷重とは、建物が支えている力のことです。屋根から2階へ、2階から1階へと、重力と同じ方向に作用します。鉛直荷重は固定荷重・積載荷重・積雪荷重の3つに分類され、それぞれの特徴は以下の表の通りです。
| 固定荷重 | 建築材による、建物自体の重さ |
|---|---|
| 積載荷重 | 人や家具などによる、建物内の床にかかる重さ |
| 積雪荷重 | 建物に積もった雪の重さ |
水平荷重
水平荷重とは、建物を横から押す力のことです。たとえば、台風の横風、地震の横揺れを受けたときは水平荷重がかかり、これらはそれぞれ「風圧力」「地震力」と呼ばれます。風圧力は建物の面が広いほどかかる力が強くなり、地震力は建物の高さや重量が大きいほど強くなるのが特徴です。

構造計算は構造安全性確認の方法の1つ
一般的な木造住宅における、構造安全性を確認する方法には以下の3つがあります。
- 仕様規定
- 性能表示計算
- 許容応力度計算
それぞれについて詳しく説明します。
仕様規定
仕様規定とは、建築基準法において全ての木造建築に義務付けられている、構法・材料・寸法などの具体的な規定です。壁量計算(壁量の確保)、四分割法(壁の配置バランス)、N値計算法(柱の柱頭柱脚の接合方法)という3つの簡易計算と、8項目の仕様ルールで構成されています。ただし、これらは最低限の簡易計算を行うための規定で、建築物の安全性を確実に担保することは難しいのが実情です。
性能表示計算
性能表示計算とは、仕様規定に定められている壁量計算に加えて、床・屋根の強度、床の強度に応じた横架材接合部の強度なども検証する計算方法です。住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で規定されており、これによって建物の耐震性能を示す指標の1つである「耐震等級2」以上を取得し、長期優良住宅や住宅性能評価の認定を受けるハウスメーカー・工務店が多いようです。
許容応力度計算
構造計算といえば、通常は建築基準法で定められたこの計算を指します。建物自体の重さや屋根に積もる雪の重さ、家具の重さ(鉛直荷重)、地震による横揺れや台風の横風などでかかる重さ(水平荷重)に対して、全ての柱や梁を検証し、建物の安全性を確かめる計算方法です。時間と費用はかかりますが、建物の安全性を確認するうえで、最も信頼のおける方法とされています。

構造計算のルートの種類3つ
構造計算には決まった計算方法(ルール)があり、これを「ルート」と呼びます。通常は専用のソフトやアプリを使って計算を行い、計算結果は構造計算書にまとめられます。構造計算書は、建物を建てる際に提出する「建築確認申請」のときに、自治体あるいは指定確認検査機関に提出するのが一般的です。
構造計算のルートは大きく3種類に分けられ、建物の規模によってどれを選ぶかが異なります。主な3種類のルートについて、以下で詳しく見ていきましょう。
許容応力度計算(ルート1)
ルート1では、建物そのものの重さ(鉛直荷重)と、地震や台風のときに建物にかかる力(水平荷重)が、使用される材料の耐力を超えないかどうかを計算します。建物が日常的に正しく機能し、自然災害時も居住者の安全が保証されるのかを確認することが目的です。
許容応力度等計算(ルート2)
ルート2は、ルート1の計算に加えて、建物の変形やバランスが特定の数値以下であることを確認する計算方法です。これにより、建物が歪んだり不均衡になったりすることなく、構造的に安定していることが保証されます。
保有水平耐力計算(ルート3)
ルート3は、大規模地震が発生した場合に、建物が部分的に損傷しても全壊には至らないことを確認する計算方法です。大規模な災害に対して、建物が一定の強度と耐久性を持つことが保証されます。
構造計算の費用
構造計算には専門的な知識が必要で作業の手間もかかるため、工務店や設計事務所が自社で行うのは難しいケースも少なくないようです。そうした現状から、構造計算は信頼できる専門会社へ外注するのがスタンダードになりつつあります。では、その費用はどのくらいかかるのでしょうか?
構造計算の費用は、主に以下の点を基準にして決められています。
- 建物の構造・規模
- 平米当たり金額
- ルート計算の難易度
実際にかかる費用は建物の構造や規模、ルート計算の難易度などによって異なり、たとえば30坪前後の住宅の構造計算にかかる費用は30万円〜50万円程度とされています。安い価格ではありませんが、法律に則った建築業務を進めるために、構造計算の費用は必要経費といえるでしょう。

構造計算の外注に困ったら住友林業アーキテクノへ
ここまで、建物の構造の安全性を担保する構造計算について解説してきました。先述の通り、2025年4月に建築基準法の改正および4号特例が縮小され、構造計算が義務化される建築物の範囲が拡大しています。構造計算の対応に追われている工務店や設計事務所も多いでしょう。
構造計算は専門性が高く複雑な作業です。専門会社への外注を検討しているものの、「どこに依頼すればいいのか分からない」「取引先が増えて管理が煩雑になるのは困る」「安心して丸ごと任せられるプロを見つけたい」といったお悩みを抱えている企業さまも多いのではないでしょうか?
住友林業アーキテクノでは、構造計算はもちろん、敷地調査や申請書作成、図面作成など、設計にかかわる重要な業務をワンストップでお引き受けする「設計業務代行サービス」を全国で展開しています。設計業務代行サービスをご利用いただければ、これまで人員不足・経験不足で対応できなかった家づくりや構法の提案全般をお任せいただけます。ご要望やご予算に合わせた部分的な業務の請負も可能です。
法改正への対応も含めて、スムーズな家づくりをサポートします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
※出典:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し、国土交通庁
(最終確認:2025年12月15日)